「ダークナイト」は最初から最後まで緊張感が続くからすごい。10年ぶりということもあるけど、二度目に見ても全然退屈しなかった。

- 発売日: 2013/11/26
- メディア: Prime Video
- この商品を含むブログ (4件) を見る
やっぱり本物のジョーカーはすごい。
俺の生活は質素だ。
趣味っていえば、ダイナマイトに火薬、そしてガソリン。その3つの共通点は?安いってこと
金なんか要らない。
これは俺がボスっていうメッセージだ。
燃やし尽くせ

人間ってのは物事が計画のうちだと平然としてる。恐ろしい計画でも。
仮に俺が言ったとしよう。「ギャングが殺される」とか「兵士が吹っ飛ばされる」とか。だれも驚かない。どれも予想の範囲内だからだ。
だが、どうでもいい市長が一人死ぬといえば――誰もが大慌て!
小さな無秩序で、体制をひっくり返す。すると世の中は大混乱に陥る。
俺は混乱の使者。何が混乱を起こす? 恐怖だ。

冒頭の銀行強盗の時からそうだったけど、常に人の行動を巧みに誘導してくる。
常に「ここにもジョーカーの仕掛けがあるのでは?」と意識しなければいけない。
警察を欺き、不可能と思われる犯罪も実行していく中で、シンパが生まれ、
そのシンパが、ウイルスのようにいろんなところに入り込んでいく。
市長銃撃の時のように、ジョーカーの攻撃を防ぐのはものすごく難しい。
もちろん警察もバットマンも十分に警戒していたし、負けてばかりではなく果敢に攻めに行っていた。
一度はジョーカーそのものを欺くことに成功してみせたかのように見えた。
しかし、ジョーカーを捕らえて安堵した直後に一瞬だけ警戒が緩んでしまい、
その隙をつかれてすべてをひっくり返されてしまう。
この辺りの感情の揺さぶりは初めて見たときは本当にびっくりした。
恐怖というものには鮮度があります。
怯えれば怯えるほどに、感情とは死んでいくものなのです。
真の意味での恐怖とは、静的な状態ではなく変化の動態――希望から絶望へと切り替わる、その瞬間のことを言う。
如何でしたか?瑞々しく新鮮な恐怖と死の味は… (fate/Zero)
一度しか使えないような秘策を使ってやっととらえたのにそれすらもジョーカーの掌の上。
あらかじめ警察署内にスパイを紛れ込ませ、自分すらも駒としてすべてをかき乱しに来る相手にどうやって勝てばいいのか。
勝利を確信した瞬間から叩き落されることもあり、この後の絶望感はすさまじかった。
ここから一気にジョーカーに好き放題されるシーンが続く。
そして、ジョーカーに引きずられる形で
・「表の世界での正義のヒーロー」になるはずだったハーヴィー・デントは復讐心を煽られて殺人を犯し
・バットマンも倫理の壁を踏み越えてしまいフォックスという最大の味方を失う。
・民衆はバットマンの仮面を脱がせるか、正体を暴こうとするリースを殺すかという
ジョーカーの意志に振り回されるだけのおもちゃと化してしまう。
・ビル突入の時でも「手下に人質の格好をさせて、人質にピエロの格好をさせる」というやり方をとっていた。
とにかく人をおもちゃにするのが楽しくてしょうがないらしい。
トロッコの実験よりこっちの「二つのフェリー」のシーン(試行回数1回の囚人ゲーム)の方が恐ろしい……
そして伝説の「二つのフェリー」のシーンに。
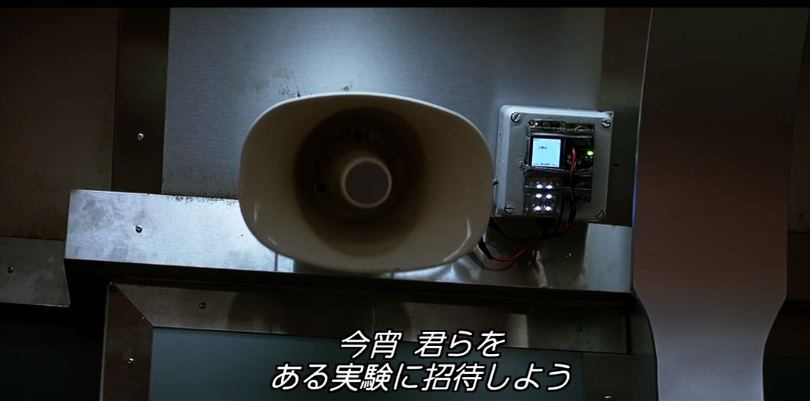
この実験のシーンを見ながら、ちょうど昨日読んだこれを思い返していた。
①「期待が行動を導く」というもので、誰かに行動をしてもらいたいとおもうならご褒美を約束して喜びを予期させるほうがいい。
配偶者をジムに行かせたいのであれば、なぜ行かないのか、と叱るよりもたまにジムにいったときに「鍛えた筋肉が素敵」と褒めるフィードバックをしたほうがいい。子どもに勉強しないとまともな仕事につけないよ、と脅すのではなく、勉強したら最終的には素晴らしい職を得て、素敵な人生をおくることができるようになるよ、とポジティブに伝えるべきだ。これは脳がそもそも機能的に「前向きな」行為を「ご褒美」と結びつけているからで、不安で煽り立てるよりも(トランプが使ったような特定の状況下以外では)基本的にはその方が人間の動作は早くなることと関連している。
②一方で、人に行動をさせたくない、抑制したいときには罰則を与えたほうが良いという結果も出ている。たとえば子どもにクッキーをあまり食べさせたくない、機密情報を口外させたくない、といった時には警告を与えたほうが良い。差し迫った脅威は、我々を凍りつかせる機能を持っているからだ。
このシーンの前までは、ジョーカーの人心掌握はすべてうまくいっていた。
ジョーカーにそそのかされて警察を裏切り、
レイチェルを死に追いやり、ハーヴィー・デントを地獄に陥れた犯人は
どちらも警官であり、それまで不正をしていたわけでもない人物だった。
しかし、「自分がやることはそこまで大したことにはならない」とか
「入院費がかさんで、これに成功したら報酬を与える」とそそのかされてそれに従ってしまう。
これは①のパターンで「希望」を与えられたり、行為の罪悪感を取り去る仕掛けがあった。
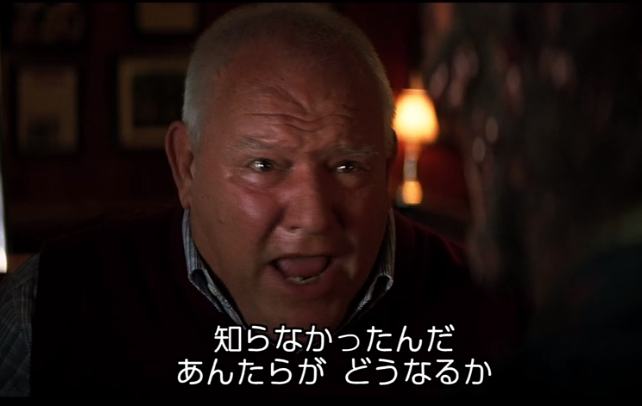
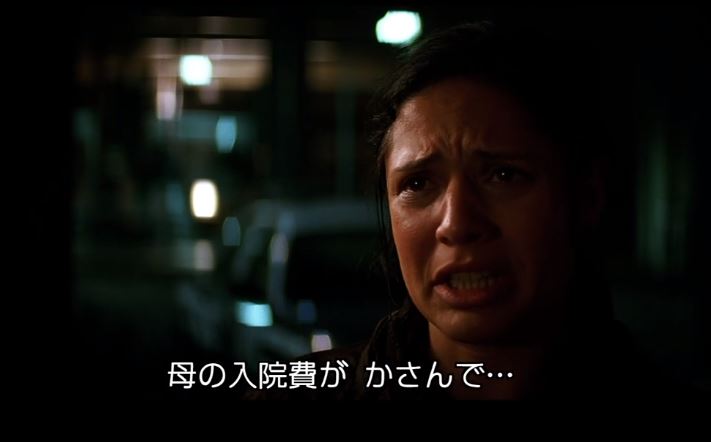
これに対して、フェリーのシーンはどうだったか。
・乗客の心を強い恐怖に晒し、人の心を「する」方向ではなく「しない」方向へと寄せていた。「あえて相手の爆破する」ではなく「助けなければ勝手に死ぬ」という状況だったら果たして結果は同じだっただろうか。
・さらに明確に自分たちの選択で大勢の人が死ぬという罪悪感も強く意識させた。「どちらか助かりたい方を選べ」とか「自分たちの守りたいものを意識しろ」と誘導することも可能だったけどそれはしなかった
・さらに、フェリー内部では軍が場を統率し、「多数決」について集団心理に流されることを防ぐため、一人一人に投票用紙を渡して「他人の意見を見ずに自分の意見を書くこと」を求めた。Twitterはこれが完全にバグっているので何も考えずに多数派につく思考停止人間が多いが、そういう思考停止の甘えたクソガキの存在を排除した。その行為にジョーカーは特に介入しなかった。
ジョーカーは、あえてこの自分の選択が選ばれるためのハードルを上げていたと考えられる。それでもなお、冒頭の銀行強盗のように「恐怖に駆られた人々はお互いが殺しあってジョーカー一人が高笑いする」というシナリオを描いていたのだろうか。
実際、投票結果は一般人の方は「賛成396票、反対140票」だった。。
私はこれ、初めて劇場で見たとき衝撃を受けたんだよね。
「スイッチを押す役が自分でなければそりゃこっち選ぶよね」って納得もしたけど、
多分この数字、思考実験か何かで実際に試した数字なんじゃないかなって思う。
あくまでも、この戦いで爆破スイッチが押されなかったのは
スイッチを押す役を引き受けた二人の人間がたまたまどちらもそれを拒否したからにすぎない。


つまりこれ、ゲームの仕組みの問題だけであって、市民はジョーカーの恐怖に負けてるんですよね。
「どちらかの船は確実に爆破される」とか「投票結果によって相手の船の爆破だけが止まる」だったらジョーカーの完全勝利だった。
ジョーカーは人の心を操ることには成功していたが「スイッチを押させる」という行為の重さを甘く見過ぎていたというだけの話。「自分がスイッチを押さなければ相手がスイッチを押さないかもしれない」という逃げ道を残してしまった(それでも勝てると思ってたんだろうけど)。

だから、この後のバットマンのセリフ「ゴッサムの市民は、お前に示した。彼らは良心を信じる善意の人々だとな。」はすごく寒々しく感じる。
実際、ジョーカーは余裕の表情をしているし、デントは悪に染まる。
楽勝さ。お前も知っての通り、「狂気」は重力のようなもの。人は一押しで落ちていく。
この残酷な世界で、唯一のモラルは運だ。運だ。運は公平で偏見もなく、フェアだ
というわけで、フェリー実験の記憶が強くてもうちょっと前向きな話かと思ってたけど
見返してみたら、終わり方はかなり寂しいものになっている。
「事実はなぜ人の意見を変えられないのか」→「誰もが自分でスイッチを押したり捨てたりの決断ができるわけじゃないから」
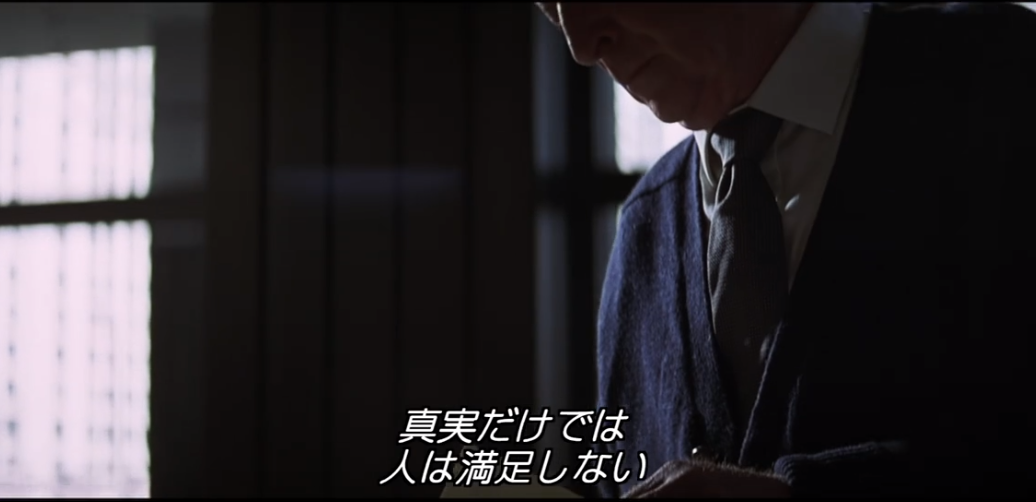
真実だけでは人々は満足しない。幻想を満たさねば。ヒーローへの信頼が報われねば。
彼はヒーローじゃない。沈黙の守護者。我々を見守る監視者。ダークナイトだ。
どうしても人はヒーローが必要で、ヒーローへの期待が報われることが必要で。
小さな真実よりも、そっちの方が大事なのだって話は、すごく胸にしみるよね。

- 作者: ターリシャーロット,上原直子
- 出版社/メーカー: 白揚社
- 発売日: 2019/08/11
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 橘玲
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 2019/07/26
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
というわけで「ダークナイト・ライジング」も今週中くらいには見て感想書こうと思います。では。



