うーん。
頭が良いフリをしてる人は“質問”に物凄く弱い。
— あだち (@adachinoaccount) 2023年7月15日
だから質問されると「そんな質問してる時点で」と内容に言及せず訊いた人を責める態勢を作ります。もしくは混乱して「何言ってんだ?」という回答をする。質問はフリを見抜けるので大事。特に相手が答えを用意できないような攻めた質問がベター。
慶應やリクル◯トみたいな正しいルーチンを徹底的に叩き込むことで頭が良いフリをしている人は空気を読めてない質問を受けると露骨に不機嫌になりますよね。 https://t.co/CBmCrZqCSm
— Shen (@shenmacro) 2023年7月15日
今まで質問するとgood questionから会話が展開する組織でしか働いたこと無かったけど、質問に対し「無駄だ」「意味が無い」「バカ」に加えお前の責任だ等の罵声を大きい声で浴びせる人が社内評価高いこともあるのだというのが近年の発見。実に愉快で楽しいので今後もたくさん質問しよう。 https://t.co/DEF9wpVYxs
— Seiichi Shiga / 志賀誠一 (@SeiichiShiga) 2023年7月15日
就活の時にリクナビ愛用してたけど「ちなみにマイナビの方が良いってポイントあります?」とマイナビに就職が決まった先輩に聞いたら「その質問してる時点で就活上手くいかないと思うよ笑」って答えが返ってきて「さてはこいつ社員の人柄とかそんなんで就職先決めたな…?」って思ったの思い出した。 https://t.co/v3IoZrO0KV
— 赤井 (@ryo_kai1202) 2023年7月15日
これで答えてくる奴もいるんだけど、
— るふと (@luftg) 2023年7月15日
その答えに内容が無く全然説明できてないという特徴がある
そしてやっぱり聞いた人を責めるのですぐ分かる https://t.co/1PjZBlb026
研究者はあらゆる質問に楽しそうに答えてくれるから好き。答えられるかどうかではなく「楽しそうに」がよきよ。 https://t.co/PjstHZDiok
— 茶 (@2tl21) 2023年7月16日
2割の人が8割の仕事をしている。
— ふろむだ (@fromdusktildawn) 2023年7月16日
と思ってた時期が僕にもあったんですが、
今となっては黒歴史です。
今なら、それが、世間知らずと高慢さが生み出した認知の歪みだと分かります。…
傾向としては確かにそういうのは感じる。
めちゃくちゃ強気で日経新聞を馬鹿にしてた人たち、名指しで質問しても誰もこたえようとしなかったし
なんというか「答えとか公式を暗記してるだけの人」ってのは確かにいると思う。
ただ、「頭が良いふりをしている人は質問にすごく弱い」だと攻撃範囲が広すぎて誤爆がきついと思うので、「正しいといわれることにも疑問を持った方が良い」くらいでどうだろう……
これについては、この前のウメハラさんの記事が言語化がうますぎてたまげてしまった。
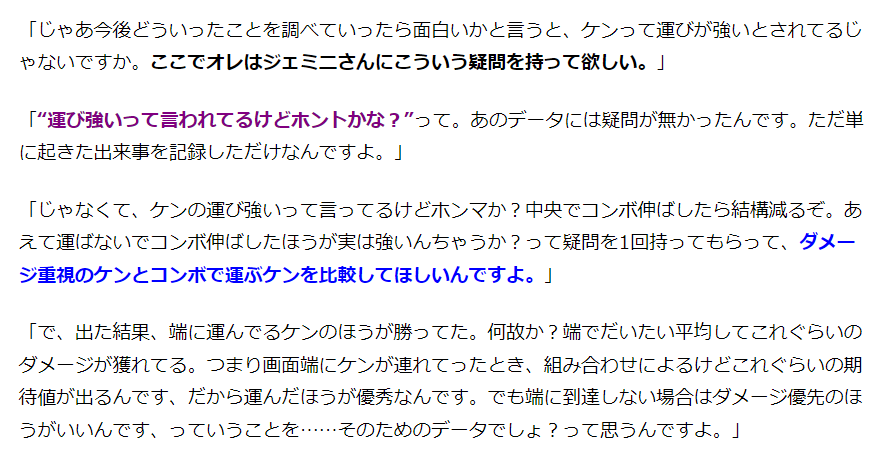
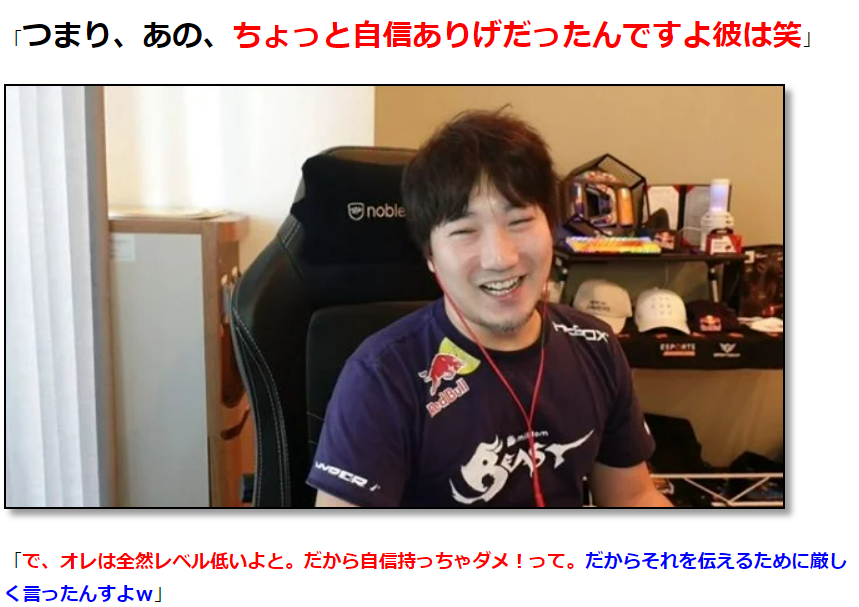
やっぱり勝ち負けの勝負で戦ってる人ってこういう感じで「詰めて」考えるんだなって思ってちょっと感動しましたね。
自分でもこの話題については思うところがあって、前から周辺をグルグル回っていろいろ記事書いてたんですよ。
www.tyoshiki.com
www.tyoshiki.com
www.tyoshiki.com
でも、ウメハラさんの記事を読んだ後「ああ、私が言いたかったのってそこだったか」って気づいたというか気づかされてしまった。
敗北感えぐい。
別に普段からここまで考えなくてもいいんだけれど、少なくとも自分の頭で考えてる人って「自分がどこまで考えていたか」はわかるわけじゃないですか。
そういう人って、他人の意見に対しても「100点満点かどうか」で評価しないんですよ。 今ここまで考えたんだな、ここからはまだだなって感じると思う。受け止め方がとても柔軟だなと思う。
逆に、自分の頭でちゃんと考えない人、公式だけ覚えてわかったつもりになってる人は態度がめちゃくちゃ硬直的なんですよ。
こういう人はいろんなところでいろんな表現をされていますが、とにかくあってるか間違ってるかはともかくちゃんと自分で考えてほしいとは思いますよね。
他人の受け売りをしている人間は、意見が合わない人と両者のなかほどの「両方のどちらにとっても同じ程度不満足な妥協点」というものをいうことができない。主張するだけで妥協ができないのはそれが自分の意見ではないからです。
虎の威を借る狐に向かって「すみませんちょっと今日だけ虎柄じゃなくて茶色になってもらえませんか」というようなネゴシエーションをすることは不可能です。キツネは自分ではないものを演じている訳ですから、どこからどこまでが虎の譲ることのできない本質でどこらあたりが「まあその辺は交渉次第である」のか、その境界線を自分で判断することができません。もし彼が本物の虎ならばサバンナで狩りをする時は茶色の方がカモフラージュとして有効ですよ、というような訳知り顔の説明をされたら一時的に茶色になってみせるぐらいやぶさかではないと判断するようなこともあり得ます。でもキツネにはそれができません。自分ではないものを演じているから。
理論的意見として、「ツーブロックは禁止。ツーブロックになると不良にからまれる」と思っている人とは、議論できます。「ホテル業界では、ツーブロックは清潔さの象徴になっている」とか「街でモニターした結果、100人中これだけの人がツーブロックだった。これだけいるのだから、ツーブロックはからまれる理由にならない」と、エビデンスを交えながら、どちらが適切か議論できます。ちゃんと議論できれば、変わる可能性はあります。でも、「校則で禁止してるから禁止」と思考停止している人とは議論が成立しません。それは、理論的思考ではなく、宗教的信仰です。「ツーブロックは禁止。それは神(校則)が決めたから」と言う人とはどんな議論もできないのです。



