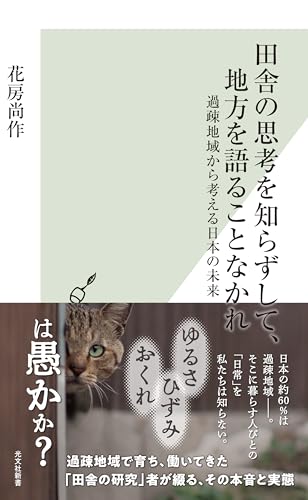信田さよ子さんの『アダルト・チルドレン』本当に本当に最高の本でした。ありがとうございます。 pic.twitter.com/ILzABunhJT
— はむすけ (@SHolmesB221) 2025年9月19日
ACは悪循環を突き破る
ACはなんでも人のせいにしていると言われますが、人のせいにすればいいと思います。
というのは、ACの人は、人のせいにできなかったからここまで苦しかったわけです。
自分であまりにも過剰に背負い込んで、自分の存在までも余分じゃないかと思い、生まれてきたことも申し訳なかったのではないかと思うくらいに。
人のせいにするところか、自分を肯定できなかったわけですから。
相手のせいにするには、相手のせいにする理由があるというある種の自己肯定がないとできないのですから、
その点から考えても、すべて人のせいにするという批判はまったく浅薄な理論です。
そんなものを気にすることはありません。
ACの人たちが「親が悪い」「親が悪い」と言えたら、一段階ステップアップしたと私は思います。
常識では、人のせいにするのはよくないことになっています。
それはなぜかというと、自分の責任を果たさないことだから。
しかし、それをいうならば、戦後五十年数年、チョイスすることもできず国際社会を渡ってきた日本で
人のせいにするなんていうことは私は何も言えないと思います。
私たちはみんな人のせいにして生きてきているわけで、
そういう意味で言えば、人のせいにできないで生きてきたACの人たちの苦しさというか、けなげさというのは
おそらくチョイスもしないで人のせいにしながら自分責任を果たさないで生きてきた日本人のいまでやりようを突き破るものではないかと思います。
それからよく言われるように、アダルトチルドレンという言葉がマスコミに登場したときに
「親が悪いと言えばすむんだろうか。甘えるんじゃない」と批判がありました。
たとえば、「そんな小さいころの、試験のときに親が鬼のような顔をしていたとか、
二八にもなって、まだぐじゃぐじゃ言って」といった物言いは当然出てきます。
しかし焦点は、そういうエピソードがなぜ残っているか、中年になってもなぜその人を苦しめているかということです。
自分が悪い子だったというふうに位置づけて、苦しんでいるわけです。
そこを一時期でも良いから、あるプロセスにおいて親が悪いと言えることによって楽になってもらおうとするのです。
そういうことを許す言葉が、その人にとってはACという言葉の意味だろうと思います。
ACはすべてを肯定する
ACというラベルは自分の状態を医学的にとらえられるという意味があります。
それは医者の下す摂食障害とか、人格障害とか、ボーダーラインなどの診断とは一線を画するどころか、遠く遠く離れたものだろうと考えています。
ACを病気だと判断する立場もあるでしょう。
医者というアイデンティティから診断するわけで、それもひとつの立場です。
でも私達は健康な部分を見つめてその部分を伸ばしていく、その人の力を信じていくという立場から病気とはとらえません。
客観性から程遠いというのがACコンセプトですから、いろいろな立場からこのコンセプトを好きに使えばいいと思います。
アディクションのアプローチの基本のひとつが、「とことんやれば先が見える」ということですから、
とことん甘えるとか、とことん逃げるとか、とことん食べるとか……。だから自分がACだと思えば、とことんACをやるといいのです。
先が見えてくるためには必要だと思います。
ACは肯定言語なのです。
なぜACが肯定言語かと言うと、まず、ACの基本である「親の支配を認める」ということからです。
マルクスの『資本論』では、階級闘争という視点から下部構造に規定された自己を認識することで、
支配を透徹した目で読み解くという内容が述べられていますが、
ACもまた、親の支配を読み解く言語なわけです。
ACという言葉は、私たちの生まれ育った家族における親の影響、親の支配、親の拘束というものを認める言葉なのです。
つまり私たちにはそういう支配を受けていまの私がいるという、
まったく純白のところから私たちが色をつけられたのではなく、
親の支配のもとにあって、影響を受けながらいまこういうふうに生きているのであって、そこを認めるということです。
自分がこんなに苦しいのは、「私がどうも性格がおかしいのではないか」とか
「私が意志が弱かったのではないか」とかということではなくて
そこには親の影響があったのだと認めることで、「あなたは責任はない」と免責する言葉でもあるわけです。
もうひとつは、自分が楽になることはいいことだと認める言葉です。
余分なものは背負わず、いやなことはしないで、もっと楽に生きようとすることはすばらしいことです。
日本人は楽になることに罪悪感を感じすぎです。
しかし、自分と親のストーリーを他者に語り、少しずつ親の存在が収縮し、親のドラマの舞台から降りた子どもは
やがては自分が主役のドラマを作り直し、親と訣別することになります。
これが、親との訣別、インナーペアレンツの駆逐です。
ここで再度、誤解のないように確認しておきますが親と訣別するといっても、決して親を捨てろということではありません。
あくまでも親が主役であるそのストーリーが変わることであり、そのドラマの舞台から降りることです。
自分の中に棲みついた親(インナーペアレンツ)に支配されて、
親の人生の共演者になっている人が、
「自分の人生の主人公」になるためのアイデンティティがACなのです。
許さなくてもいい。憎んでもいい。
闘ってもいいし、折り合いをつけてもいいし、駆逐しても良い。
自分を主人公にするには親を「自分のストーリーの登場人物」として整理できればいいのです。
このように、内なる親と訣別するためには、自分が作ってしまっている親とのドラマを語りつづけなければなりません。
語りつづけるうちに、そのドラマのストーリーは、必ず変わるからです。
そして、語ることのできる安全な場所を求めることです。
私の感想
とても良い話だと思います。
あとはこれをSNS上でやらず、ちゃんとお金を払って専門家相手にやることを徹底してくれれば言う事はない。
これはあくまでも「癒やしのための物語」なのだから。
本人の主観では真実であっても「客観性のない嘘」なのだから。
その約束を共有してくれる人、それを嘘として扱ってくれる人と以外に拡散すると「癒やしのための物語」が「ヒトを殴るための棍棒に性質を変えるから。
私はSNSにおける毒親ツイートがツイフェミ以上に嫌いなので、ああいうのをオープンなSNSで撒き散らす人はもはや被害者じゃなく加害者だと認識しています。
こうた。うう、大きな声で泣いちゃう….😭 pic.twitter.com/Z71lcfPa51
— ずんずんのずんずんいこう(╹◡╹) (@zunzun428) 2025年9月19日
この本、確かになぁ、と思うことばかりだった。
— あーす (@chiri_lady_ino) 2025年9月19日
都市からみた「地方」の見方が偏っているし、現状を変えるべきだとは思うが、社会の変化を嫌う人が多くなっている中では難しいのかも、と思ったり。
色んな政策が地方の実態を踏まえたものにはなっていないなぁと再認識できた。#読了 pic.twitter.com/zFjGTCbqKj