について自分なりに考えてみて・・・それを読み物にしてみました(ナンデ?)
読み物の構成
これについてA(石丸アンチ)とB(再生の道については理解を示している人)が意見を戦わせている会話です。
A:党首が石丸でなければ「再生の道」のハイスペックな人材たちは当選できた! 石丸に力をもたせるべきではないとか、石丸を支持するような人間には票をやりたくないという人達の声が大きかった。そもそも都知事選のときは石丸支持者が160万票だったのに、今回の再生の道立候補者全体でも40万票。石丸はオワコンだ!
B:むしろ再生の道から立候補してネットで知名度を高めたからこれだけの票が取れたのだ。個人ではチャンスがなかったのにここまで健闘できたのだから石丸さんのちからはすごい!
ただ、最終的にどちらも石丸伸二個人については否定するような作りになっています。
タイトル部分の「なぜ不快感を与えるのか」の答えだけ知りたい人は第二部だけ読んでください。
ここからスタート
「再生の道で落選した候補者の経歴を一通り見てみた。公認会計士、医師、三菱商事、住友不動産、大手製薬会社、大手証券…と錚々たるハイスペ名門企業がズラリ…。みんなマジで辞めちゃったの⁈そんな中で30代女子を二人見つけたのでピックアップしてみた。東電に住不、この人手不足の時代に勿体無い…」
このSNSへの投稿をきっかけに、旧知の仲であるAとBは、ある日の夜、オンラインで議論を交わしていた。Aはややシニカルな現実主義者、Bは物事を多角的に見ようとする分析家タイプだ。
【第一部:石丸伸二と「再生の道」――評価の分水嶺】
A: 「なあ、B。さっきのSNSの投稿、見たか?『再生の道』の候補者たちだよ。あの錚々たるメンツ、本当に人生賭けて飛び込んだんだろうけど、結局ほとんどダメだったじゃないか。俺はね、やっぱり石丸伸二、あいつが元凶だと思うんだよ」
B: 「元凶、か。また手厳しいな、Aは。確かに結果だけ見れば、議席獲得には至らなかったケースが多いんだろうけど、そこまで単純に言い切れるかな?」
A: 「単純さ。都知事選の時は160万票だっけ? あれだけメディアも持ち上げて、新しいリーダーだなんだって騒いだけど、今回の『再生の道』全体の得票数、伝え聞くところによれば40万票程度だったって話じゃないか。激減だろ。結局、石丸に力を持たせるべきじゃないとか、石丸を支持するような人間、ああいう攻撃的なスタイルについていけないって思った有権者が多かったんだよ。あのハイスペックな人たちが、石丸じゃなければ、もっとまともな党首のもとだったら、当選できた可能性だってあったんじゃないか?石丸はもうオワコンだよ」
B: 「うーん、その見方には一理あるかもしれない。石丸さんのスタイルは、確かに熱狂的な支持者を生む一方で、同じくらい強い反発も招くからね。特に、既存の政治秩序を重んじる層や、彼のやや挑発的な言動を好まない層にとっては、彼が党首であること自体がマイナスに働いた可能性は否定できない。だけど、A、視点を変えてみようよ。そもそも、あの『再生の道』の候補者たち、石丸さんがいなかったら、あれだけの注目を集められたと思うかい?」
A: 「そりゃ、全くの無名よりはマシだったかもしれないが…」
B: 「マシどころじゃないと思うよ。彼らの多くは、それぞれの分野では優秀なんだろうけど、政治の世界ではほとんど無名だ。そんな彼らが、個人でいきなり国政選挙や大きな地方選挙に打って出て、どれだけの票を獲得できる? 下手したら供託金没収の連続だよ。『再生の道』という看板、そして何より石丸伸二という良くも悪くも強力な磁場があったからこそ、ネットを中心に彼らの存在が認知され、あの40万票という数字に繋がったとも考えられる。個人ではほとんどチャンスがなかった人たちが、石丸さんの知名度と発信力に乗っかることで、ここまで『健闘』できた、と見ることもできるんじゃないかな」
A: 「健闘ねえ…。都知事選の160万票からの40万票を健闘と呼ぶのは、さすがに無理があるだろ。支持者が4分の1に減ったってことじゃないか」
B: 「そこは選挙の種類が違うから、単純比較は危険だよ。都知事選は、候補者個人の知名度やキャラクターがダイレクトに票に結びつきやすい首長選挙だ。メディア露出も桁違いに多い。石丸さん個人への期待、あるいは既存政治への不満の受け皿としての役割が、あの160万票に繋がった。一方で、今回の『再生の道』が戦ったのが、仮に衆議院選挙や地方議会選挙だとすれば、そこでは政党の組織力、候補者個々の地盤、そしてより具体的な政策が問われる。新興の政治団体にとっては、都知事選のような個人戦とは比較にならないほどハードルが高いんだ。だから、40万票という数字を『激減』と断じるのは早計で、むしろ、全くのゼロからスタートした新党が、これだけの票を獲得できた背景には、やはり石丸さんの影響力があったと見るべきじゃないかな。石丸さんの『ちから』が、無名の新人たちにスポットライトを当てた側面は無視できないよ」
A: 「まあ、確かにそう言われれば、無名の新人がいきなり出てきて戦うよりは、石丸という看板があった方がマシだった、という理屈は分かる。だが、その結果がこれじゃあ、結局、石丸の神通力もそこまでだったってことだろ。ハイスペックな人材を揃えても、党首のイメージが悪ければ勝てないという、典型的な例になっただけじゃないか」
B: 「神通力というよりは、彼の求心力と発信力の限界、あるいはその使い方の問題だったのかもしれないね。都知事選で得た個人の人気を、どうやって党全体の支持に転換していくか、その戦略が十分じゃなかった可能性はある。ただ、『党首のイメージが悪ければ』と一概に言うけれど、彼に魅力を感じて集まった候補者や支持者も確実にいたわけだから、そこは評価が難しいところだ」
【第二部:ISM48と新しい政治参加の形――期待と失望の狭間で】
A: 「結局のところ、石丸のやってたことって、『ISM48』みたいなもんだったんじゃないか? 石丸プロデューサーがいて、その周りに彼を信奉するメンバーが集まって、メディア戦略で話題を作って…。候補者一人ひとりの政策や理念よりも、石丸伸二というブランドが前面に出過ぎてた。あの『見せ方』『演出』、つまり戦術としての『How』の部分は、ある意味で巧みだったのかもしれないけどな。だが、それだけだ」
B: (深く頷きながら)「『ISM48』か。確かに、うまいこと言うね、Aは。その『見せ方』、つまり『How』の部分は、これまでの既成政党にはない新しさや、ネット時代の注目を集める手法としては、ある種斬新だったし、目を引いたのは事実だ。だが、僕がどうしても看過できないのは、もっと根本的な、そして致命的な部分なんだよ。石丸伸二という人間、そして彼が率いた『再生の道』には、決定的に『ミッション』が欠けていた。いや、存在しなかったと言ってもいい」
A: 「ミッション! まさにそれだよ! 普通、何かを成し遂げようとする時、特に人を巻き込むような大きなプロジェクトなら、まず『何を成し遂げたいか』という確固たるミッションがあるべきだろ。企業がブランドを構築する時だってそうだ。最初に『我々は何のために存在するのか』というブランドプロミス(公約)とかミッション(理念・志)ってよばれるものがあって、その次に『誰のために(Who)』、そして『どんな価値や未来を提供するのか(What)』があって、最後に具体的な手段としての『どうやって実現するのか(How)』が来るはずだ。石丸には、この一番重要なミッションも、WhoもWhatも、全く見えてこなかった。あるのは、ただ表層的な『How』=若者への政治参加を促すだけを主張していた。なぜ、若者が政治参加すべきかという目的部分を語らず、それ自体が目的であるかのように語るのは、随分と人をバカにした話だ。 それを鵜呑みにする若者もどうかと思うけど。」

B: 「その通りだ。単に『公約を具体的に掲げない』という戦術的な話で済まされる問題じゃない。政治家である以上、『誰の、どんな困難を解決し、幸せにしたいのか(Who)』、そして『この国や地域を、具体的にどういう状態にしたいのか、どんな理想の社会を実現したいのか(What)』という明確なビジョンを示すのは、最低限の義務であり、責任のはずだ。それを曖昧にしたまま、あるいは意図的に語らずに、『俺のやり方についてこい』と言わんばかりの『How』だけを振りかざすのは、有権者を愚弄しているとしか思えない。まるで、中身のないイメージだけの、しかし見栄えだけは良いコマーシャルを延々と見せられているような不快感があったよ」
A: 「その通りだ。政治はエンタメじゃない。人を導くリーダーシップというのは、まず明確な旗印、つまりミッションを掲げることから始まる。この選挙に限らず、彼のこれまでの市長としての言動や、メディアでの発信を見ていても、一貫して『Who』や『What』が驚くほど希薄なんだよな。常に『自分がどう動くか』『どう注目を集めるか』『どう敵を論破するか』という、戦術論や自己演出、つまり『How』の部分ばかりが異常に強調される。ミッションがない人間、ビジョンを描けない人間は、残念ながらリーダーの器じゃない。どれだけ個々の能力が高く、弁が立ったとしても、それは誰かの明確なミッションの下でこそ、初めて建設的に活きる。だから、石丸は本来、トップに立つべき人間ではなく、有能なナンバー2や参謀役、あるいは特定のプロジェクトを遂行する実務家であるべきなんだ」
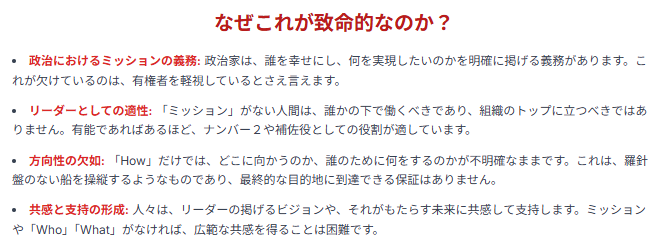
B: 「ナンバー2か…。確かに、彼の情報分析能力や問題発見能力、そしてあの強烈な実行力は、明確なビジョンとミッションを持つリーダーの下でなら、優れた参謀として、あるいは特命プロジェクトの推進役として、大きな力を発揮したかもしれない。だが、A、彼の性格を考えると、それもまた難しいんじゃないか? あの強烈な自己顕示欲と、時に他者を見下すかのような傲岸とも取れる態度を見ていると、彼が誰かの下で謙虚にナンバー2に甘んじ、リーダーを支える役に徹することができるとは、到底思えないんだが」
A: (苦笑しながら)「だよな。そこがまた厄介なところだ。プライドが高すぎて、人の下につくなんてまっぴらごめんだろう。自分が常に中心で、スポットライトを浴びていないと気が済まないタイプに見える。結局、ミッションもなく、他者と真に協調することもできず、ただ『How』の巧みさや目新しさだけで人を惹きつけようとする。そんな人間がトップに立って何かを動かそうとすること自体が、社会にとって、あるいは彼に期待を寄せた人々にとって、極めてリスキーだと言わざるを得ない。だから、俺は結論として、石丸が関わるものは、どんなに斬新で、面白そうに見えたとしても、その根幹にあるミッションの不在を理由に、絶対に肯定すべきではないし、応援するべきではないと強く思う。あの『再生の道』に集った、元の投稿にあったようなハイスペックな候補者たちには同情する部分もあるが、彼らもまた、その『ミッションなきHow』という名の蜃気楼に巻き込まれた、ある種の被害者だったのかもしれない」

B: 「そうだね…。仮に、石丸さんがやろうとしたことの中に、Aが最初に言ったような『ISM48』的な手法、つまり新しい政治参加の形を模索するという『How』の側面があったとしても、その根幹にあるべき『ミッション』『Who』『What』の致命的な欠如、そしてリーダーシップの資質に対する根本的な疑問が、全てを台無しにしてしまっている。どんなに斬新で効果的に見える手法も、向かうべき明確な目的地と、それを示す揺るぎない羅針盤、つまりミッションがなければ、ただの漂流にしかならない。今回の『再生の道』の試みは、残念ながら、その典型的な失敗例として記憶されることになるのかもしれないね。だからこそ、あの『How』の面白さに目を奪われることなく、その本質を見抜く必要がある。そして、私たちは、ああいった形のムーブメントには、明確に『ノー』を突きつけるべきなんだ」
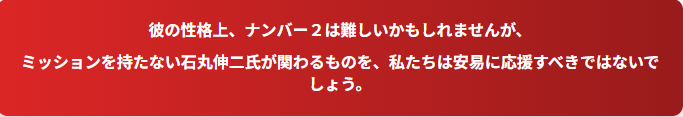
A: 「そうなんだよ。あのハイスペックな経歴を持つ人たちが、本気で日本を良くしたいと思って、安定したキャリアを捨ててまで飛び込んだんだろうからな。その情熱や能力が、石丸という個人のキャラクターによって潰されたり、矮小化されたりしたんだとしたら、それこそ『勿体無い』話だ」
B: 「その『勿体無い』という感覚は、多くの人が共有しているかもしれないね。だからこそ、次のステップが重要になる。石丸さんの試みから何を学び、何を反面教師とするか。そして、本当に新しい政治参加の形をどうやって作っていくか、だ」
【第三部:三バンの壁――有能な個人の絶望的な戦い】
A: 「しかし、だよ。石丸云々を抜きにしても、今の日本の選挙で、有能な個人が勝つっていうのは、本当に難しいよな。結局、ものを言うのは『地盤・看板・鞄』の三バンだ。親から受け継いだ強固な後援会組織(地盤)、党の公認や知名度(看板)、そして莫大な選挙資金(鞄)。これらを持たない人間が、いくら志が高くて能力があっても、勝負にならない」
B: 「それは、日本の選挙制度の構造的な問題だね。特に国政選挙や大都市の首長選挙になると、その傾向は顕著だ。例えば都知事選を個人で戦うとなると、まず供託金だけで300万円。それに加えて、ポスター作成・掲示、選挙事務所の維持、選挙カー、ビラ、ネット広告、スタッフの人件費…考えただけでも気が遠くなるような費用がかかる。これを個人で賄える人間はごく少数だよ」
A: 「金だけじゃない。組織だよ。都内全域に自分の政策を訴え、有権者一人ひとりと対話し、支持を広げていくなんて、個人の力じゃ不可能に近い。既存政党は、長年かけて築き上げてきた地方議員のネットワークや、業界団体、労働組合といった支持母体を持っている。これに対抗できる組織を、新人が一代で築き上げるなんて、夢物語だ」
B: 「メディア戦略もそうだね。テレビや新聞といった既存メディアは、どうしても実績のある現職や、主要政党の候補者を中心に報道する。無名の新人が十分な露出を得るのは難しい。そうなると、ネットでの発信に頼らざるを得なくなるけど、ネットだけで全有権者層にリーチするのは、まだ限界がある」
A: 「だから、元の投稿にあったみたいに、東電だの住友不動産だのを辞めてまで出てきた人たちが、結局この『三バンの壁』に跳ね返されて落選していくのを見ると、何とも言えない気持ちになるんだよな。彼ら彼女らが、もし既存の大政党から公認を得ていたら、あるいは強力な地盤を引き継いでいたら、結果は違ったかもしれない。でも、それでは『新しい政治』とは言えないだろうし…」
B: 「まさにジレンマだね。既存のシステムに乗れば当選の確率は上がるかもしれないけど、それは結局、既存の政治力学に取り込まれることにもなりかねない。かといって、全くの個人で理想を掲げて戦っても、多くは『ドン・キホーテ』のように扱われてしまう。この構造をどうにかしない限り、本当に多様なバックグラウンドを持つ有能な人材が、公平に政治に挑戦できる環境は生まれないだろう」
【第四部:ネット選挙の功罪――注目至上主義と怪しいインフルエンサー】
A: 「で、三バンがないと、どうなるか。結局、手っ取り早く注目を集めるために、ネットでの露出や過激なパフォーマンスに走るしかなくなるんだよな。最近の選挙を見ていると、政策の中身よりも、いかにバズるか、いかに炎上するかで注目度を上げようとする候補者が増えてきている気がして、正直うんざりする」
B: 「それは否めないね。ネットは、資金力や組織力に劣る候補者にとっては、貴重な情報発信のツールであると同時に、注目を集めるための競争が激化しやすい場所でもある。結果として、より刺激的な言葉遣い、より奇抜な行動が、有権者の目に触れやすくなるという側面がある」
A: 「その結果、出てくるのが、例えば『さとうさおり』氏みたいなタイプ、とでも言えばいいのかな。特定の個人を指しているわけじゃないけど、ああいう、政策的な裏付けよりも、YouTuber的なキャラクターや扇情的な主張で人気を集めようとする候補者だよ。あれが選挙なのか?って思っちゃうね。政治がどんどんエンターテイメント化して、ショービジネスみたいになっていくんじゃないかっていう危機感がある」
B: 「『さとうさおり』氏的な存在、というのは象徴的だね。ネット上での知名度やフォロワー数が、そのまま政治的な影響力や信頼性に繋がるわけではないのに、一部ではそういう誤解も生まれているかもしれない。もちろん、ネットを巧みに活用して、真摯に政策を訴え、支持を広げている候補者もたくさんいる。でも、Aが懸念するように、表面的なパフォーマンスやスキャンダラスな話題ばかりが先行して、政策論争が深まらないという傾向は、確かに心配だ」
A: 「有権者側も問題だよな。面白いかどうか、刺激的かどうかで投票先を決めるような風潮が広がったら、それこそ民主主義の危機だ。政策の実現可能性や、候補者の資質、倫理観といった、もっと本質的な部分を見極める力が求められているのに、情報が多すぎて、何が本当で何がフェイクなのか、見分けるのも難しくなってきている」
B: 「ネット選挙は、情報の拡散スピードが速い分、デマや誹謗中傷もあっという間に広がるリスクを常に抱えている。候補者も有権者も、メディアリテラシーを高めて、冷静に情報と向き合う姿勢が、これまで以上に重要になっているのは間違いないね」
【第五部:ワンイシュー政党の行方と政治不信の先に――私たちが望む未来】
A: 「あと、最近気になるのが、参政党みたいな、いわゆるワンイシュー政党、あるいは特定のイデオロギーに強く偏った政党が増えてきていることだ。もちろん、特定の課題に光を当てること自体は悪くないんだけど、国の運営って、そんなに単純な話じゃないだろ? 一つの答えだけが正しい、みたいな主張は、どうも危うさを感じるんだよ」
B: 「ワンイシュー政党の台頭は、いくつかの側面から考える必要があると思う。一つには、Aが言うように、複雑な社会問題をあまりにも単純化して捉え、特定の解決策だけを絶対視する危険性があること。また、時に排外的な主張や、科学的根拠の乏しい情報、陰謀論的な言説と結びつきやすい傾向も指摘されているね。これは、社会の分断を助長しかねない」
A: 「そうなんだよ。ワクチン問題とか、特定の歴史認識とか、そういうセンシティブなテーマで、過激な主張を繰り返して支持を集めようとするやり方は、見ていて不安になる。もっと建設的な議論が必要なのに、感情的な対立ばかりが煽られているような気がする」
B: 「ただ、一方で、そうした政党が出てくる背景には、既存の主要政党が、国民の多様な声や、切実な不安を十分に受け止めきれていない、という現実もあるんじゃないかな。政治不信が深まる中で、自分たちの声が届かないと感じている人々が、より先鋭的で、分かりやすいメッセージを発する政党に惹かれる、という側面もあるのかもしれない」
A: 「それは分かる。今の政治に閉塞感を感じていて、何かを変えたい、でもどこに託せばいいのか分からない、という有権者の気持ちは理解できる。だからこそ、まともな選択肢がもっと増えてほしいんだよ。過激な主張や、実現不可能な公約を掲げるのではなく、現実的な課題解決能力と、誠実な対話の姿勢を持った政治家や政党が、もっと評価されるべきだ」
B: 「結局、石丸さんのやり方や『再生の道』の試みは、多くの課題を残したかもしれないけれど、彼らが投げかけた『既存の枠組みにとらわれずに、新しい力で政治を変えよう』という問いかけ自体は、重要だったと思う。その方向性を、もっと洗練された、より多くの人の共感を得られるような形で、誰かが引き継いでいく必要があるんだろうね」
A: 「そうだな。あの『再生の道』に集ったハイスペックな人たちが、もし別のリーダーのもと、別の戦略で戦っていたら、どうなっていただろうか、と想像してしまうよ。有能な個人が、地盤・看板・鞄の壁に阻まれることなく、純粋に政策とビジョンで勝負できて、当選できるような選挙のあり方、政治のあり方に、少しでも近づいていってほしいと、切に願うよ」
B: 「そのためには、僕たち有権者一人ひとりが、もっと賢くならなければいけないね。何が本質で、何が単なるパフォーマンスなのか。誰が本当に社会を良くしようとしているのか、それを見抜く目を養い、そして、諦めずに声を上げ続けること。それが、結局は政治を変える一番の力になるのかもしれないな」